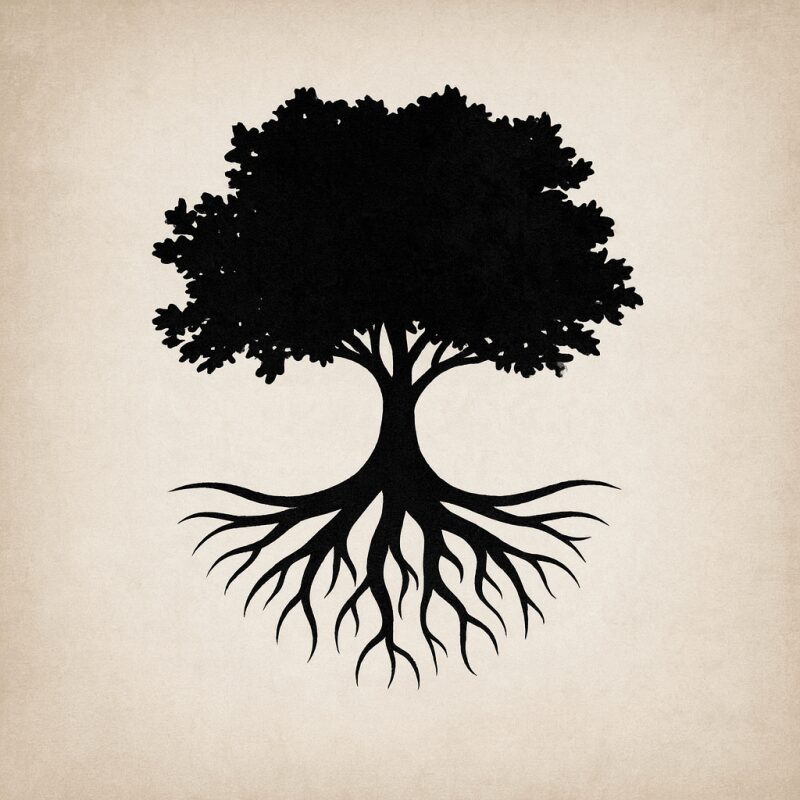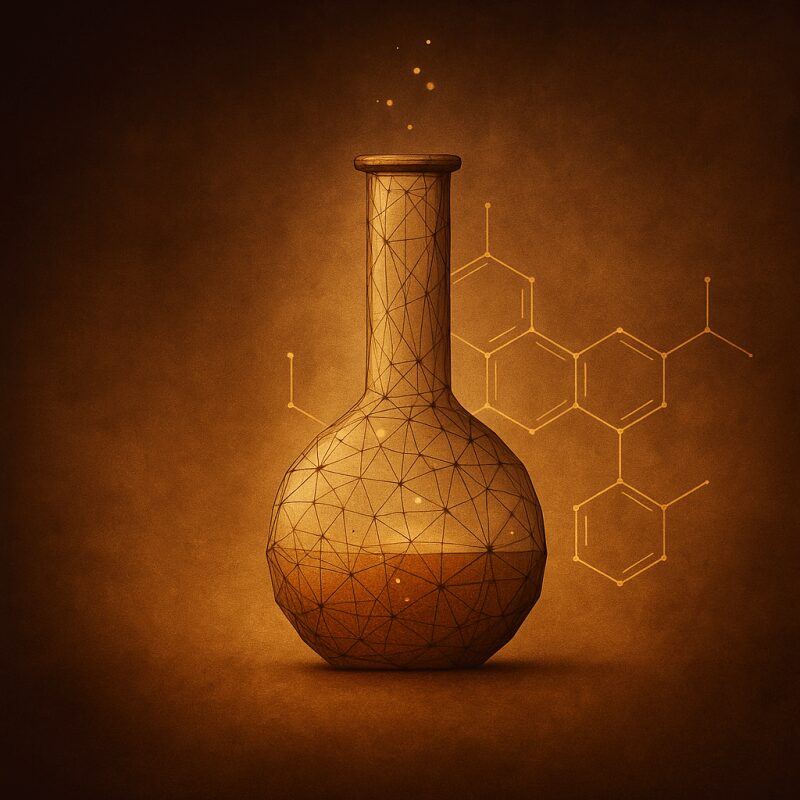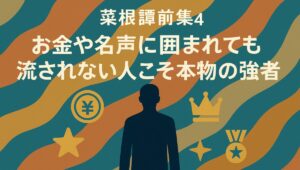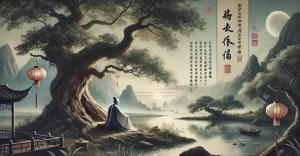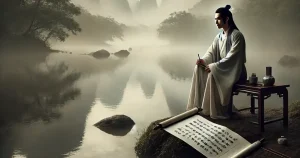『菜根譚(さいこんたん)』は、中国・明の時代の思想家・洪自誠(こうじせい, 1573–1620)が著した処世訓の書。
日本では織田信長が活躍し、徳川家康が江戸幕府を開いた頃、同じ時代に生きた人物です。
現代は便利になった反面、簡単に手に入る答えが、人の考える力を奪っています。
結果として、いざ困難に直面したとき、心のしなやかさが無くなってしまいます。
ほとんどの人は今まで過ごしてきた中で、そんな経験が大小少なからずあるのではないでしょうか?

『菜根譚』は、「菜根を嚙みしめる苦みに、人生の真の味わいがある」と教えてくれます。
楽をして得られる人生の喜びは浅く、歴史の荒波を越えて読み継がれてきた『菜根譚』そのものが、その真実を物語っています。
技術がどれほど進歩しても人は結局、自分自身の内に立ち返り、心の深みに向き合うことを求められているのです。
『菜根譚』は、儒教・道教・仏教の三つの思想が融合しており、逆境に耐える力・平穏を楽しむ心・人間関係を整える知恵が凝縮されています。
なぜ今「菜根譚」なのか
AIを使用したイメージです
現代は、SNSや仕事の重圧によって「心がすり減る」時代です。
嫉妬や妬み、自分の無力さ、それらは期待と現実の間に生じる影ともいえます。
もちろん職場や友人関係だけでなく、家族や親族といった身近なつながりの中にも生まれ、私たちを悩ませます。
そんな時、『菜根譚』は静かに語りかけてきます。
- 苦境をどう受け止めるか
- 欲望や衝動をどう制御するか
- 心をどう静めるか
といった問いに答えてくれる、普遍的な人生の教科書。
自分の中で解決できないこと、誰かに相談しても解決できないこと、アナタの悩みを和らげてくれます。
歴史を通じ愛読されてきた菜根譚は、いつでもアナタの味方でいてくれ、導いてくれる本なのです。
菜根譚の科学的な裏付け
AIを使用したイメージです
菜根譚の最初の一節にこのような言葉が出てきます。
道徳を守る者は、一時の寂しさを味わう。
権力に媚びる者は、末永い虚しさに苛まれる。
賢者は、目先のことに囚われず、遠い未来や死後を思う。
ゆえに、一時の寂寞を受け入れ、長き虚無を避けるべきである。
一言でいうと、「一時の孤独を避けると、自分らしく生きられない」と、なります。
さらに解釈を深めれば、これは「報酬の先送り」を説いているとも言えます。
1960年代後半から1970年代前半、スタンフォード大学で行われた有名な「マシュマロ実験」というのがあります。
子どもに「今すぐ1つ食べるか、少し我慢して2つもらうか」を選ばせ、待つことのできた子どもほど、その後の学業・行動・健康で良好な成果を示すことが追跡研究で明らかになりました。



この実験は賛否あるようですが、「目先の利益に騙されるな」といった研究は幅広く検証されています。
つまり、歴史を通じて人が繰り返し実感してきた知恵は、現代科学の実験によっても裏づけられているのです。
菜根譚と古典との響き合い
AIを使用したイメージです
菜根譚の教えは、他の古典思想とも共鳴します。
- 紀元前5世紀:孔子『論語』(義 vs 利)利益の追求に偏ると社会や人間関係が乱れる。
- 1~2世紀:エピクテトス(内面の自由)「何が起きるか」ではなく「どう受け止めるか」が自由を決める。
- 4世紀:アウグスティヌス(神の愛に従う自由)信じることと考えること、両方が大事。
- 6世紀:ボエティウス(真の幸福は内面にある)落ち着いた心こそ、本当の幸せ。
- 9世紀:空海(宇宙と心の一体)心を静めれば宇宙とつながる。
- 13世紀:鴨長明(無常と自然への帰依)自然の中で静かに生きるのが安心。
- 18世紀:カント(原則・義務の哲学)大事なのは正しい理由で行動すること。
- 1989年:コヴィー『7つの習慣』(原則中心の生き方)誠実さ・責任感・信頼といった普遍のルールが大事。
菜根譚の教えもまた、この長大な系譜の探究の一環であり、静かながらも力強く時代を越えて響き続けているのです。
時代も文化も異なるのに、同じ真理が繰り返し語られているのは、それが人間にとって本質的なテーマだからです。
古今東西、私たち人は同じ悩みを感じていたのです。
まとめ
「菜根譚」とは、逆境をも受け入れ、平穏を楽しみ、心を整えながら生きるための知恵です。
古典でありながら、現代科学や哲学とも共鳴し、今を生きる私たちに深いヒントを与えてくれます。
管理者も毎日、My菜根譚のページをめくりますが常に新しい発見があります。
菜根譚はアナタの悩みにそっと、寄り添ってくれるはずです。