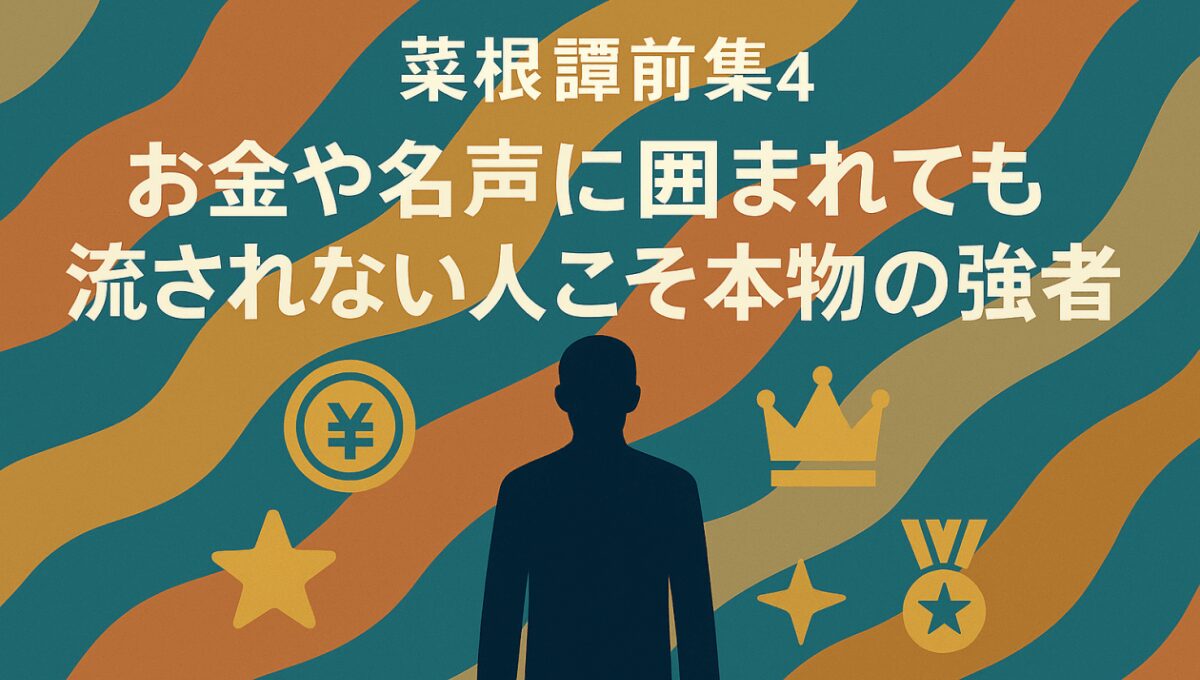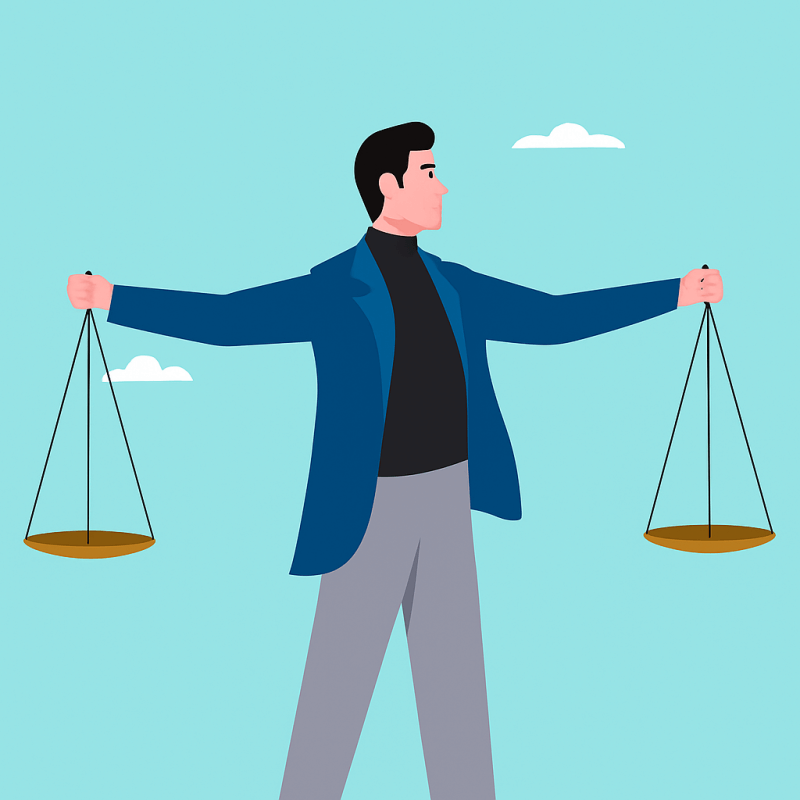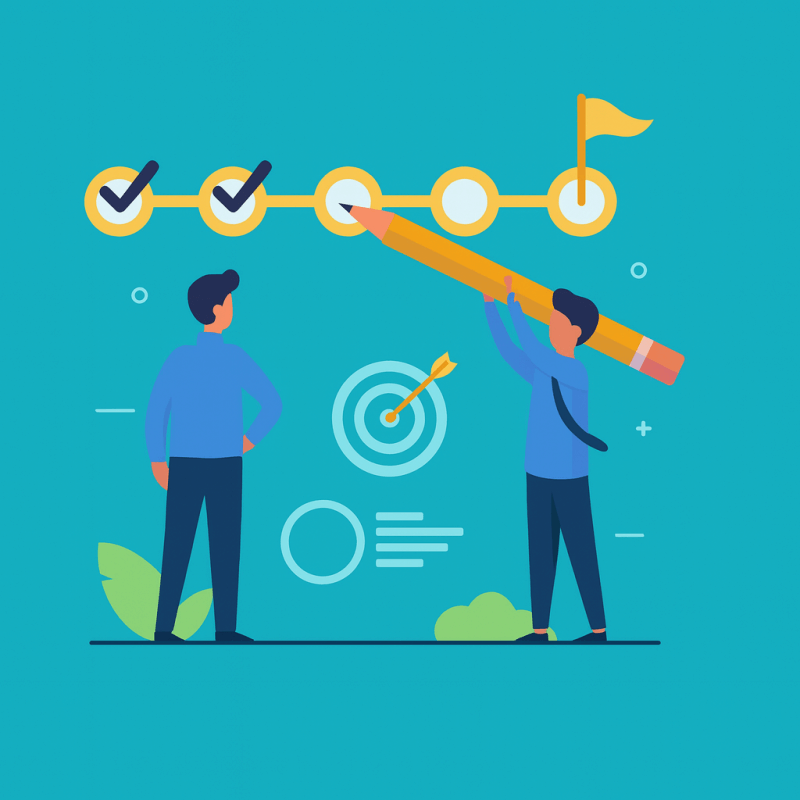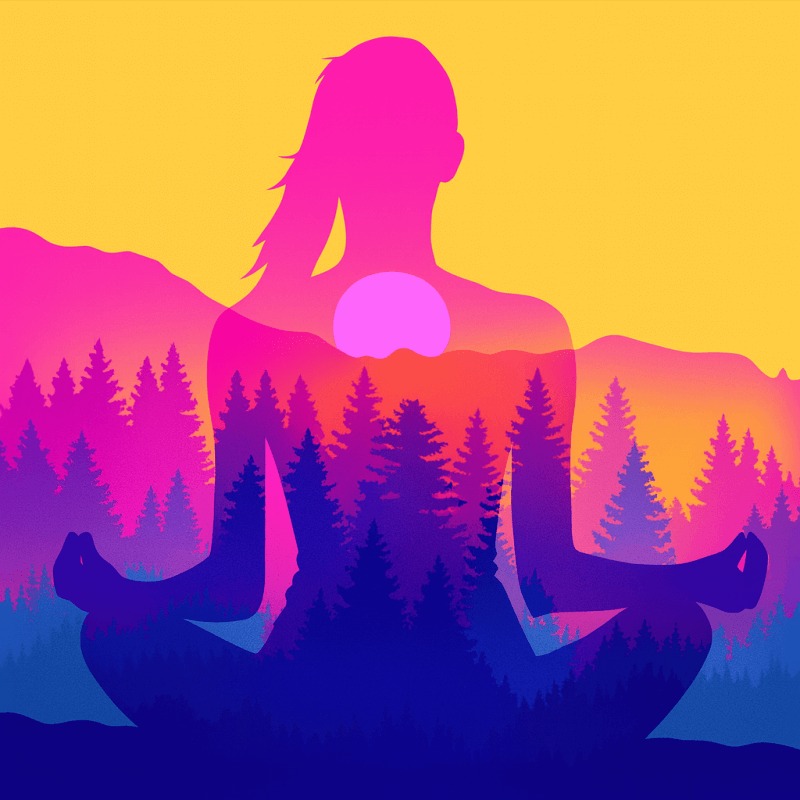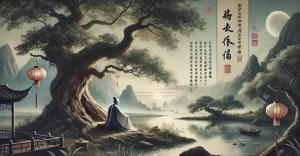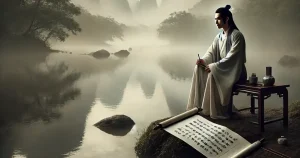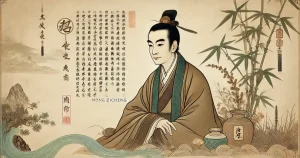キラキラしたお金や名声というのは、刺激的であるものの常に海水を飲んでいるみたに、それだけでは真に満たされているとはいいがたい状況に陥ります。
SNSには他人の華やかさだけを切り取った日常が、所せましと埋め尽くしているのが現状です。

しかし、華やかさ一時、一瞬の繁栄でしかありません。
現代社会では、他人のキラキラした言動から逃れることはなかな難しいですよね。
菜根譚は、キラキラに近づかないことを良しとし、近づいたとしても惑わされないことを最良と説いています。
明治維新の立役者でありながら、富や権力に執着せず、新政府の地位を辞して鹿児島に帰郷した西郷隆盛。
誘惑に抗い、世の中の道理を優先した人物として有名です。
今回は、原文の解釈と科学的エビデンス、偉人も併せて惑わされない生き方を紹介していきます。
【菜根譚前集4】原文と現代語訳
AIを使用したイメージです
菜根譚の前集4節の原文こちら、



勢利紛華、不近者為潔、。近之而不染者為尤潔
智械機巧、不知者為高、知之而不用者為尤高。
補足
「勢利(せいり)」:権力やお金、地位などのこと。
「紛華(ふんか)」:うわべの繁栄や浮ついたもの。
「智械機巧(ちききこう)」:頭の良さを悪用した、ずる賢い策略や小賢しい知恵。
現代文で解釈すると、
- お金や名声から距離を置くことは立派なことです。けれど、本当に強いのは、それを持ちながらも心を乱されない人です。ズルいやり方を知らない人は素直といえます。でも、それを知っていながら選ばない人こそ、人として一段上の境地にいるのです。
- お金や地位から離れて生きるのも立派ですが、持っていても振り回されないことの方が、もっと大切です。ズルいやり方を知らないのは無邪気な証拠。けれど、それを知っていても選ばないのが、本当の大人の姿です。
自分の価値を認められたいがために、やっきになっていませんか。
管理者もまったくもって同意します。
自慢や高慢な態度は相手を不快にしてしまうのは勿論、予期せぬレッテルを張られるのこともよくあることです。
この句でも語られているとおり、人間関係を良好にするために過度な主張は避けたいものです。
【菜根譚前集4】敬天愛人を抱いて生きた
Wikipedia
お金や権力を遠ざけ、人の為に尽力した人として、あげられるのが西郷隆盛。
1828年に薩摩藩(現在の鹿児島県)に下級武士の家に生まれます。
薩摩藩はもともと贅沢は避け、質素を尊ぶ教育がなされていました。
九州南部は京都や東京といった消費が大きな中央とは離れていたので、交易から利益をえる経済活動が不利な地域。
薩摩藩は江戸時代になると参勤交代による藩の財政圧迫により、無駄を避け倹約を美徳とする質実剛健な土壌がさらに育っていきます。
江戸時代に入ると、薩摩藩は「郷中制度」を整備し、藩士の子どもたちは必ずこの教育を受けるようになりました。
「郷中制度」とは年齢ごとに役割が決まっていて、年長者が年少者を指導する「相互教育」の形をとっていました。



教えの中心は学問よりも、人格形成・武道鍛錬・共同体の規律。
そんな制度があったから、薩摩藩からは西郷隆盛や大久保利通など、忠義とリーダーシップを兼ね備えた人材が育ったのでしょう。
島津斉彬の銅像
Wikipedia
西郷隆盛は気質もあったのは言うまでもありませんが、藩主の島津斉彬に才能を認められ後の倒幕運土の立役者になっていくことに。
江戸城の無血開城、そして新政府では軍政や人材登用に尽力していくことになります。
しかし、政府の急速な近代化政策や征韓論をめぐって意見が対立。
1873年には辞職し、鹿児島へ戻り私学校を設立、若者の教育と人材育成に取り組んでいくことになります。
明治維新後、武士の身分は廃止され、廃刀令(1876年)で帯刀も禁止。



武士の身分がなくなった士族たちは不満を募らせ、自然と西郷隆盛の元に集まってくるようになります。
この頃は、各地で士族による反乱が発生。
新政府の中心だった西郷隆盛の元に人が集まってくるこに、中央は目を光らせていました。
そのため、鹿児島に残っていた旧藩時代の兵器を大阪の造兵廠(軍需拠点)へ移そうと計画。
士族はその計画を知ると怒りを爆発させ蜂起、西南戦争(1877年1月29日)の直接的なきっかけとなっていきます。
Wikipedia
西郷隆盛はこの戦いで、トップに担ぎ上げられていますが、交戦には反対していました。
反乱軍は近代兵器を備えた新政府軍に苦戦。
西郷隆盛は9月23日に自刃、西南戦争が終結します。
結局は反乱軍のトップになってしまいましたが、勝海舟や弟、従者たちの証言でも「政府と話し合う」ために上京するつもりだったと記録があります。
多くの歴史学者は、
- 西郷隆盛の意思:転覆の計画はなかった
- 士族たちの行動:不満が爆発し、結果的に反乱へと発展
- 新政府の認識:国家体制への挑戦として反乱と断定
と、西郷隆盛の意志と時代の流れがかけ離れていたのが妥当だとの見解です。
江戸城の無血開城に貢献した際にも、当時150万人のいわれた江戸での市街戦を避けることが至上命題でした。
後世の人たちが「最後のサムライ」と慕っているのは、野心よりも誠実な人格ゆえに、時代に押し流された悲劇の人と見なされているからです。
タイトルにある「敬天愛人」ですが、明治の啓蒙思想家の中村正道の造語、「天を敬い、人を愛する」という意味で、西郷隆盛は座右の銘としていました。
【菜根譚前集4】お金と成功は価値があるのか?
AIを使用したイメージです
現代社会では、お金や成功を手にすることが「価値ある人間の証」と思われがちです。
しかし、アメリカの心理学者のPark らの研究(PMID: 28903640)によると「自分の価値をお金に結びつけるほど、心は揺れやすくなる」ことを示しています。
- お金で自分の価値を測る人ほど、不安やストレスが強く、自律性が下がる
- 金銭的に脅かされる場面で、問題から目をそらす回避行動が増える
- 他人との比較に敏感になり、孤独感や人間関係の質が下がる
インターネットの発達によりお金を稼ぎやすくなっている一方、心を病んでしまう人も多く存在します。
つまり、自分の本当の価値観にあった行動をしていないからに、他ならないからでしょう。
さらに、SNSでのキラキラに反応してしまい、自身が劣っていると感じ、自己嫌悪に陥ってしまいます。
逆に、お金や名声に流されない人こそ、本物の強さを持っていることも明らかになっています。
- 内面的な価値観(大切にしていること)
- 人とのつながり(関係性)
- 自分の成長感(有能感)
自分の価値をお金や名声に依存させない人は、自律性を保ち、ストレスにも柔軟に対応できることが示されました。
心理学でいう「レジリエンス(心の回復力)」との関係しています。
【菜根譚前集4】
AIを使用したイメージです
お金や名声に流されてしまうのも、自分の中でルールが無いのが問題。
宝くじ当選者が急に大金を手にして数年後に破産、社会的名声を得て傲慢になり人の信用を失うといった、ケースをよく耳にします。
人の欲望は底なし沼より深いので、歯止めが利かなくなり抜け出せなくなった結果でしょう。
しかし、人間には理性というものがあり、その力を使うことでより良く生きることができます。
理性の保ち方を哲学者の生き様、科学の視点からまとめてみました。
理性を保つためには習慣を大切に
AIを使用したイメージです
流されることを避け、理性を保つために習慣を大切にした哲学者として有名なのが、イマヌエル・カント。
1724年4月22日、プロイセン王国のケーニヒスベルク(現在のロシア・カリーニングラード)に誕生。
1804年2月12日に79歳で生涯を閉じますが、なんと、出身地からほとんど出ることなく同じ町で、過ごしたことも有名です。
現代でもあまりどこかに出かけないのに妙に物知りな、おじいちゃんっていますよね。
カントの専門は哲学ですが、自然科学や物理学にも興味を持ち、初期にはニュートン力学の影響を受けた論文も執筆しています。
ちなみに、レオナルド・ダヴィンチも多岐にわたる才能を発揮していますが、カントの時代も学問の垣根があまりなかったようです。
そんな、多彩な才能を発揮していたカントですが日常生活は習慣を非常に重要視していました。
AIを使用したイメージです
彼は毎日同じ時間に散歩へ出かけ、その規則正しさは「カントが歩き始めたら時計を合わせられる」と言われるほどでした。



カントの几帳面さは、性格ではなく「欲望や気分に流されず、理性によって自分を律すること」。
頭でっかちの学者ではなく、習慣は実践を伴った学びだったのです。
カントが提唱した「定言命法」という有名な原則があります。
「自分の行動が“世の中のきまり”になったとしても誇れるかどうか考えよう」
自分の行動がみんなの行動原則(法律やマナーのようなもの)になっても良いか?
といったことを自問自答してから行動しよう、ということです。
この考えは、お金や名声、快楽に左右されず、自らの理性を信じて行動する生き方と深く結びついています。
SNSの情報で簡単に気持ちが揺さぶられる現代。
カントのように極端に行動することは大変でしょうが、時間を決めてSNSを見る習慣をつけるのも、良い方法かもしれませんね。
マインドフルネスで理性を保つ
AIを使用したイメージです
心を落ち着かせ理性を保つのに一番簡単なのが、マインドフルネスです。
簡単に言うと、



呼吸に意識しよう
と、いうことです。
心拍、血圧、消化などの自律神経系は、基本的に無意識で動いていますが、呼吸だけは意図的に操作できます。
呼吸のリズムを変えると、心拍、血圧、交換・副交感神経のバランスに影響を与えることを、多く研究報告があります。
そして、全然難しくなくマインドフルネスの方法として「スローブリージング」というものがあり、



1分間に10回程度(約6秒に1回)、呼吸をゆっくりする
だけで、ストレスが低下するという研究(PMID:30245619)があります。
マインドフルネスの注目ポイントが、
- いつでもどこでもでき、道具がいらない。
- 胸や腹の動き、空気の感触で感覚的にわかりやすい
- 呼吸の調整を通じて心身を落ち着ける生理学的経路が自律神経系とつながっている。
- 注意を「今ここ」きっかけとして使える。
多くの人の悩みが、過去の後悔や、未来への不安。
マインドフルネスは、今ここに集中することができ、今やるべきことに没頭する手がかりとなってくれます。
毎日、1分で良いのでマインドフルネスの呼吸を習慣にすることで、お金や名声といった外の評価に囚われない自分を形成する手助けをしてくれるはずです。
まとめ
お金や名声といった「キラキラ」は一瞬の刺激にすぎず、それだけでは心を満たしてくれません。
『菜根譚』前集4は、権力や富に近づかない清らかさ、近づいても染まらないさらに深い清らかさを説いています。
西郷隆盛やカントのように、欲望や流行に流されず、日々の習慣で自分を律した偉人たちの姿は、その生き方を体現しています。
現代ではSNSを通じて他人の華やかさが絶えず流れ込んできますが、本当の強さは外の評価に囚われず、自分の価値観や理性に従って生きること。
その土台となるのが「良い習慣」と「心を整える練習」です。
毎日ほんの1分のマインドフルネス呼吸やSNS使用時間のルール化など、シンプルな習慣から始めるだけでも、心は静まり理性を保ちやすくなります。